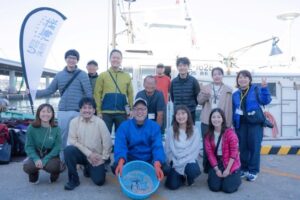10月24日は 「世界ポリオデー」 ― 不要なハガキ ・ 切手で、 途上国の子どもたちへワクチン支援
SDGsフォーカス 机の引き出しに“命を救うチャンス”がある。 認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)は、10月24 … 続きを読む日本人口の7.6%がLGBT…左利き、AB型と同数、日本の六大苗字よりも多い
2017.11.14 (火)
国内でのLGBTへの注目が加速したのはいつから?
藥師さん自身は、女性の身体で生まれ、男性と自認するトランスジェンダー。幼少期から性別に違和感があり、小学校6年生で性同一性障害という言葉を知ったという。初めてカミングアウトしたのは高校2年生の時で、大学1年生からは男性として生活し、2009年に現団体の前身団体である「早稲田大学公認学生団体Re:Bit」を設立。それから約8年ほど経過しているが、日本社会のLGBTに対する認識や風向きはどのように変化してきたのだろうか。
藥師さんは「団体を立ち上げた当初、“LGBT”という言葉は、多くの方が知らなかった印象です。今ではLGBTを取り上げてくださるメディアも増えてきましたが、数年前までは、メディアの方もどう表現したらいいか分からないような状態でした。風向きが大きく変わった契機はいくつもありますが、その中でも、渋谷区と世田谷区の『パートナーシップ制度』の発表は大きかったと感じます」と説明。
東京都の渋谷区と世田谷区は2015年9月5日に、「パートナーシップ制度」開始を発表。条例成立は東アジアで初めてとなり、世界的なニュースとしても報じられた。
同制度は、法的拘束力はないが、婚姻関係と同等のものとして自治体が証明。渋谷区は「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」、世田谷区は「世田谷区パートナーシップの宣警の取扱いに関する要項」。渋谷区の場合はパートナー証明書が発行され、同性パートナーシップであることを渋谷区が認めるという条例。一方、世田谷区では受領書が発行され、同性パートナーが世田谷区に対して宣警し、世田谷区長が受理するという要項である。
「この制度を発表したことによって、各自治体が『同性パートナー』について議論に挙げやすくなった。行政が動きを受け、企業も動き始めた。証明書を持ってきた社員がいたら福利厚生はどうなるのか? お客様が持ってきたら家族向けのサービスはどうするのか? といった点です」

そしてもう1つ、日本国内におけるLGBTへの社会的に熱量が高まったのが、2020年の「東京オリンピック・パラリンピック」の開催決定と、藥師さんは指摘。2017年3月24日には「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コード」が承認され、具体的に性的指向や性自認に関わる差別の禁止が盛り込まれた。
人権の項目の概要では、以下のように記載されている。
「組織委員会は『このオリンピック憲章の定める権利および自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会のルーツ、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない』というオリンピック憲章の理念を強く支持する。また、ダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包摂性)の観点を重視する」
また、人権の詳細項目では、「社会的少数者(マイノリティ)の権利尊重」についても記載されている。
「サプライヤー等は、調達物品などの製造・流通等において、民族的・文化的少数者、性的少数者(LGBT等)、移住労働者といった社会的少数者(マイノリティ)の人々の権利を、他の人々と同様に尊重し、それぞれの特性に応じたプライバシー保護にも配慮しつつ、これらの人々が平等な経済的・社会的権利を享受できるような支援に配慮すべきである」
当然、「2020東京オリンピック・パラリンピック」の公式スポンサーは、調達コードを遵守しなければならない。これをひとつのキッカケとして、『マイノリティ』に配慮する企業が増えることは嬉しい事です。他にも、LGBTの問題を考える超党派の議員連盟の発足や、LGBTに関する法案の提出など、2020年まで、そしてそれ以降に向けた様々な動きがあります」と藥師さんは明かす。
社会的には追い風が吹いているようだが、LGBT当事者はそもそもどのような考えを持っているのか?
藥師さんは「約13人に1人いるLGBTの人ですので、人それぞれさまざまな意見をもっています」と返答。
「しかし、安心して自分らしく働けたり、住めたり、暮らせることを願っていることは共通しています。その社会の実現のためには、多くの人がLGBTについて知る機会が増えることが必要。身近にいないと思うことで偏見が生じてしまったり、無意識に傷つけてしまうことも少なくありません」
最初から拒絶するのではなく、まずは知ること、互いにコミュニケーションをとることが最善。小さな一歩を踏み出すことが必要だ。
特定非営利活動法人「ReBit」
オススメ記事
“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。
SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む
SDGsフォーカス
兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!
SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む
過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!
SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む
大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!
SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む
“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。
SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!
SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!
SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!
SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む