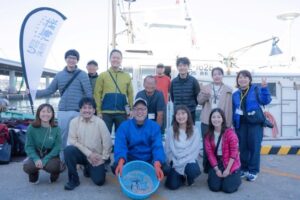10月24日は 「世界ポリオデー」 ― 不要なハガキ ・ 切手で、 途上国の子どもたちへワクチン支援
SDGsフォーカス 机の引き出しに“命を救うチャンス”がある。 認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)は、10月24 … 続きを読むSDGsフォーカス
お茶の水女子大がトランスジェンダー学生受け入れへ! その意味をお茶大生と考えてみた
2018.08.03 (金)
とまどいは否めないけど、女子大だからできることがある

▲豪田ヨシオ部インターン、お茶の水女子大学4年生のガッキー
お茶の水女子大学は学則で入学資格を「女子」としています。これまでその定義はされてなく、問い合わせがあった場合、「戸籍の性」と答えてきましたが、2020年度入学試験の出願資格からは、「戸籍または性自認が女子」となります。
戸籍と性自認が異なるトランスジェンダーの受験希望者には、出願前に申し出をしてもらい、出願資格を確認し、入学後の様々な問題について本人と相談するとしています。そのために、「受け入れ委員会」を立ち上げ、「対応ガイドライン」の作成を進めます。昨年発足したワーキンググループは、大学の執行に関わる人達、各学部の代表者、トランスジェンダーの専門家で構成され、今回の決定まで検討を重ねてきました。受け入れ委員会はそのメンバーを拡大した形になるそうです。
記者会見後に質疑応答の時間が設けられ、各メディアからは、性自認の確認方法や、トイレをはじめ施設設備の整備についての質問が集中しました。
医師の診断書や第三者の書類が必須かという質問に対して、「トランスジェンダーは性同一性障害だけでなく、広い範囲の学生が含まれるので、診断書等を提出できる方にはそうしていただくが、それが難しい方には、本学で学びたいという真摯な希望をしっかりと受け止めて判断したい。その方法は受け入れ委員会で詳細に検討する」と室伏学長。また、「多様な価値と人々が交錯する社会に出て行くこれからの学生にとって、お茶の水女子大学が真摯に学びを求める全ての女性に門戸を開き、その成長を支援する環境を築くことが、強い力になる」と学長が話したことが、私には印象的でした。
豪田ヨシオ部インターン、お茶の水女子大学4年生のガッキーは、今回の決定を受けて友達と話しました。正直、とまどいはあるそうですが、女子大学だからできることがあると彼女は言います。
高校までずっと共学だったガッキーは、女子大だからではなく、自分が学びたい分野の専門の先生がいたのでお茶の水女子大学を選んだそうです。入学後に強く感じるのは、文系の学生であっても理系の学生が取るような授業を受けることができたり、それにジェンダーの問題が絡んだり、ジェンダーについて考える機会が多いこと。
私の知り合いにもお茶の水女子大学出身者が何人かいるけど、前身の東京(高等)女子師範学校から142年以上の歴史を持つお茶大生には、時代を切り開いてきたという自負があると感じます。
「女性活躍の時代と言われているけれど、まだまだ変えていかなければと室伏学長は記者会見で話されたのだと思いますが、私は共学の大学に進んでいたら『変えていこう』という意識にはならなかったかもしれない」とガッキー。女性が変える、女性が変わる、そして男性も変わる、その原動力になるという意味で、歴史的意義だけでなく、現代も女子大が存在する意義はあるとガッキーも私も思います。
今回のトランスジェンダー学生受け入れ決定も、共学校だったら目に見えにくかったかもしれない。女子大学だから可視化(という言葉が相応しいかどうかわからないけれど)したのかもしれないと、各女子大学の取り組みを知って、私は感じます。
世界経済フォーラム(世界1,200以上の企業・団体が加盟)によるジェンダーギャップ指数 が144カ国中114位の日本社会。社会課題を見出し、解決していく学生、リーダーを育む女子大学の存在意義が今、試されているのかもしれません。
先日、杉田水脈衆議院議員が、性的マイノリティの方たちについて「生産性が無いので公的に支援するのはおかしい」と雑誌誌面で語ったことがニュースになり、批判が集まりました。ご存知の方も多いわよね。この「生産性」という言葉が子どもを作らないことを指すのであれば、性的マイノリティだけに向けられた問題ではなく、介護されている人、障がいを持つ人、様々な事情を抱えて子どもを作らない人にも向けられた差別的な発言だと私は思います。
発言の自由だとか個人の人生観だとかを理由に杉田さんの発言を擁護する意見もあったけど、本当にそうかしら? この社会に生きる一人一人にはそれぞれの生き方があるという尊厳をないがしろにするような発言は、いかがなものかしら?
大学生の皆さんは、リペラルアーツ教育のもとで様々な教養を身につけますよね。それは単なる知識ではなく、自分で自分の考えや言葉を検証し、「これでいいのだろうか?」と振り返って考える能力。それが本当の教養や見識というものではないかしら。誰かの尻馬に乗るのではなくてね。
今回のトランスジェンダー学生受け入れの決定は、2015年に国連サミットが採択したSDGsの5)「ジェンダー平等を実現しよう」はもちろん、4)「質の高い教育をみんなに」、10)「人や国の不平等をなくそう」にも関わることじゃないでしょうか。
「これでいいのだろうか?」と「じゃあ、こうしていきませんか?」を、私たち豪田ヨシオ部は考え、活動を続けていきたいと思います。
オススメ記事
“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。
SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む
SDGsフォーカス
兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!
SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む
過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!
SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む
大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!
SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む
“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。
SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!
SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!
SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!
SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む