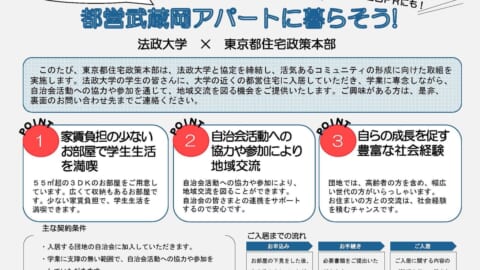冬の寒さに負けず熱戦!荒川河川敷を一掃! 「第23回 大学対校!ゴミ拾い甲子園」レポート!
イベントレポート 6月に続き、今年最後のゴミ拾い対決!大学生が荒川の河川敷を一掃する環境活動「第23回 大学対校!ゴミ拾い … 続きを読む教えて、豪田ヨシオ部! NPOの悩みを解決! 大学生の情報収集の極意
早稲田大学3年 ぺき
2017.12.15 (金)
76.1%の学生はFacebookをやっていない!? 聞いてみなければ分からない若者のSNS事情
*▲情報元:「第9回大学対校! ゴミ拾い甲子園」でのSNSに関するアンケート調査
*▲本文に掲載した円グラフは2017年12月10日(日)に実施した「第9回大学対校! ゴミ拾い甲子園」でのSNSに関するアンケート調査結果です。
「SNSに情報を投稿しているのに、なかなか若者の間で団体の認知度が高まらない」
今、NPOの方々は、大学生をはじめとする若年層に向けた情報発信において課題を抱えています。“社会貢献”という切り口においても発展途上国の支援や国内での被災地復興ボランティアなど、興味関心のある分野は学生によって様々。多種多様な興味を持つ、彼らの心をグッと掴む情報を発信することは至難の業です。実際に今回のイベントに参加されたNPO職員の男性は「大学生ってどんなオンラインサービスを使っているの?」「何時に投稿すれば情報が学生の目に留まるの?」といった疑問を持っていました。
「大学生向けに社会貢献の情報を発信している豪田ヨシオ部の学生さん、ぜひ若者のSNS事情を教えてくれませんか? みなさんのリアルな声はNPOの課題解決にきっと役立つはずです」
NPOなど公益活動団体の情報発信を支援する日本財団CANPANプロジェクトの山田さんが豪田ヨシオ部へ直々に依頼をしてくださったことをキッカケに、今回のイベント開催が決定しました。日本財団といえば「みんなが、みんなを支える社会」を目指し、国内・海外を舞台に様々な社会貢献活動を展開する日本を代表する公益財団法人。企業・NPO・政府・国際機関に働きかけている日本財団に所属するCANPANプロジェクトの方々にお声を掛けていただいたということもあり、フォーラムに向けていつも以上に気合が入りました。
パネリストを務めたのは私、ぺきと豪田ヨシオ部の部員で東海大学3年生のイガくん、ウダガワくん、ナカノさん、専修大学3年のヒラタさん。そしてアドバイザーには豪田ヨシオ部プロデューサーの畑中さん、コーディネーターにはNPOのいろはを知り尽くした日本財団CANPANプロジェクトの山田さんが登壇し、イベントはスタートしました。

▲参加者の方々に注目され最初はちょっぴり緊張気味…。

▲ほんわか笑顔で学生・参加者を和ませてくれた山田さん。
まず、話題に挙がったのは、ふだん学生が使っている連絡手段について。なんと5人中全員が真っ先に連絡ツールとしてLINEを挙げました。更に、連絡手段の代表格ともいえるメールについては、使用頻度があまり多くないということも新たな発見。特に、私とイガくんに関してはメールチェックを暫くしなかったために、1000件以上もの未開封のメールが溜まってしまった経験も! この結果についてはコーディネーターの山田さん、参加者の方々もびっくり。企業のCSR担当として働く女性は「溜まりに溜まったメールの中に私たちのメルマガも紛れ込んでいるのかもしれないですね…。私たち大人の視点からは分からない新たな発見です!」と仰っていました。NPOで大学生の会員やイベント参加者1人1人と連絡を取りたい場合、個人LINEをすることで若者からの返信率アップが期待できるかもしれませんね。では、不特定多数の人に情報を発信することに適している、3大SNSのFacebook・Twitter・Instagramについてはどのように使っているのでしょうか?

・「第9回大学対校! ゴミ拾い甲子園」のアンケート調査では、Twitterを利用する学生が最も多い。
・「SNSを何個も駆使する自信がない」という方は、Twitterに絞るのも1つの手段かも。
まずFacebookに関しては意外にも使用率が5人中、私1人とかなり低め。私自身、最近は半年以上投稿しておらず、自分にとってFacebookは馴染み深いSNSとは言えません。一方、コーディネーターの山田さんをはじめ参加者の多くは、3大SNSの中でFacebookの使用頻度が最も高いようです。実名性が高く信頼性も十分担保されているため、ビジネスシーンで利用されることも多いFacebook。ただ、学生にとっては「国際協力などに興味がある意識の高い若者が使っているSNS」というイメージが強いようです。確かに、個人のFacebook投稿で目立つのは、特別なイベントに参加した際のレポートなど“ちょっぴり意識高め”な近況報告や、社会に対する自分の意見・想いなど。なるほど、確かに何か特別なネタがある人のみぞ投稿する、“1段敷居の高いSNS”という印象を受けます。
もともと社会貢献意識の高い学生に向けてピンポイントで情報を発信したい場合は、特にFacebook投稿に力を入れるのも1つの策かもしれませんね。

・7割以上の学生はFacebookを使っていない。意識の高い学生にターゲットを絞った情報発信がポイントになる。
3大SNSの中でも学生からの支持が最も高かったのはTwitter。ヒラタさん、ナカノさん、ウタガワくんの3人がTwitterを使っていました。総務省の「平成29年版 情報通信白書 ICT白書2017」によれば2016年における10代のTwitter利用率は61.4%、20代が59.9%。若者にとってかなり身近なSNSと言えるでしょう。

▲出典:「平成29年版 情報通信白書 ICT白書2017」第1章スマートフォン経済の現在と将来
(http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/pdf/n1100000.pdf)
Twitterユーザーのヒラタさんは「満員電車辛い」など、自分の何気ない想いを言葉にするほか、過去の出来事を見返すための日記代わりとして利用しているそうです。また、ウタガワくん、ナカノさんについてはめったにツイートせず、タイムラインを眺めていることが多いそう。自分のことについて積極的に情報発信している学生は、意外と少数派なのかもしれませんね。

・3大SNSの中で最も利用率が高いTwitterも基本的にタイムラインを眺めるだけの学生が多い
・情報が流れていきやすいため、印象に残る投稿が成功の秘訣
またInstagramユーザーについては私、ナカノさんのみでした。「インスタ映え」という言葉が流行語大賞に輝くほど、世間では絶大な人気を誇るInstagram。その一方、中野さんは以前Instagramをよく利用していたようですが、最近は流行に乗るのが嫌であえて使わないようにしているそうです。私自身、投稿したのはたったの2回だけ。芸能人やトレンドに敏感な友達のインスタを見る分には楽しいものの、自分自身はフォトジェニックな写真を撮る機会に恵まれず、投稿が滞りがちになるケースもあります。投稿数が極端に少ない場合、活動していないと見なされてしまう可能性もあるので、無理にアカウントを作る必要はないかもしれませんね。

・ゴミ拾い甲子園の参加者は男子学生が比較的多いためか、半数以上の学生がInstagramを利用していない。
・投稿数が極端に少ない場合、活動していないと思われてしまう可能性もあるので、無理にアカウントを作らなくてもいいかも。
オススメ記事
【大学生×SDGs】27大学・過去最多455人が参加!あの大学が3連覇「大学対校!ゴミ拾い甲子園」第22回開催レポート
イベントレポート 6月8日に東京都荒川の河川敷にて、昨年に続き「第22回 大学対校!ゴミ拾い甲子園」が開催されました! 会場となった … 続きを読む
青春×エコのSDGsイベント「第22回大学対校!ゴミ拾い甲子園」6月8日開催!
イベントレポート 大学対校でごみ拾い!?大学生がチームを組んで環境美化に挑む「第22回大学対校!ゴミ拾い甲子園」が今年も開催決定! 楽しみ … 続きを読む
【レトロこみちのノスタルジックな魅力編】関西と関東の大学生が兵庫県洲本市で関係人口創出のためのアイデアを提案
イベントレポート 「豪田ヨシオ部」は9月27日(金)~29日(日)の3日間、洲本市役所の協力のもと、兵庫県企画部地域振興課が主催する『地域 … 続きを読む
【洲本市民広場とレンガ造りの建物群編】関西と関東の大学生が兵庫県洲本市で関係人口創出のためのアイデアを提案
イベントレポート 「豪田ヨシオ部」は9月27日(金)~29日(日)の3日間、洲本市役所の協力のもと、兵庫県企画部地域振興課が主催する『地域 … 続きを読む
【静岡県西部エリア】Z世代が静岡県の新たな魅力を発見&動画制作! ネット検索では出てこない情報や魅力を発信「将来的に静岡県に住みたいと思ってもらいたい!」
イベントレポート 「豪田ヨシオ部」は、首都圏在住の若者の視点で静岡県の様々な取組や魅力を発信するプロジェクト「静岡県 首都圏若者広報業務 … 続きを読む
【静岡県伊豆エリア】Z世代が静岡県の新たな魅力を発見&動画制作! 観光スポットの新たなPR手法をイメージ「魅力を足して進化していける場所」
イベントレポート 「豪田ヨシオ部」は、首都圏在住の若者の視点で静岡県の様々な取組や魅力を発信するプロジェクト「静岡県 首都圏若者広報業務 … 続きを読む
【大学生×SDGs】27大学・過去最多455人が参加!あの大学が3連覇「大学対校!ゴミ拾い甲子園」第22回開催レポート
イベントレポート 6月8日に東京都荒川の河川敷にて、昨年に続き「第22回 大学対校!ゴミ拾い甲子園」が開催されました! 会場となった … 続きを読む青春×エコのSDGsイベント「第22回大学対校!ゴミ拾い甲子園」6月8日開催!
イベントレポート 大学対校でごみ拾い!?大学生がチームを組んで環境美化に挑む「第22回大学対校!ゴミ拾い甲子園」が今年も開催決定! 楽しみ … 続きを読む【レトロこみちのノスタルジックな魅力編】関西と関東の大学生が兵庫県洲本市で関係人口創出のためのアイデアを提案
イベントレポート 「豪田ヨシオ部」は9月27日(金)~29日(日)の3日間、洲本市役所の協力のもと、兵庫県企画部地域振興課が主催する『地域 … 続きを読む【洲本市民広場とレンガ造りの建物群編】関西と関東の大学生が兵庫県洲本市で関係人口創出のためのアイデアを提案
イベントレポート 「豪田ヨシオ部」は9月27日(金)~29日(日)の3日間、洲本市役所の協力のもと、兵庫県企画部地域振興課が主催する『地域 … 続きを読む【静岡県西部エリア】Z世代が静岡県の新たな魅力を発見&動画制作! ネット検索では出てこない情報や魅力を発信「将来的に静岡県に住みたいと思ってもらいたい!」
イベントレポート 「豪田ヨシオ部」は、首都圏在住の若者の視点で静岡県の様々な取組や魅力を発信するプロジェクト「静岡県 首都圏若者広報業務 … 続きを読む【静岡県伊豆エリア】Z世代が静岡県の新たな魅力を発見&動画制作! 観光スポットの新たなPR手法をイメージ「魅力を足して進化していける場所」
イベントレポート 「豪田ヨシオ部」は、首都圏在住の若者の視点で静岡県の様々な取組や魅力を発信するプロジェクト「静岡県 首都圏若者広報業務 … 続きを読む